はじめに|「株の引き継ぎ」で困る時代が来ている
中小企業の経営者として、会社の未来をどう託すか──これは避けて通れないテーマですね。
「そろそろ息子に事業を継がせたい」
「幹部社員に株を渡して代表にしたい」
こうした事業承継の場面で、実は多くの社長がつまずくポイントがあります。
それが、“株式にかかる贈与税・相続税”の問題です。
中小企業の株式は、思いのほか高く評価されることがあります。
その結果、後継者が数百万円〜数千万円単位の税金を請求され、支払えずに苦しむケースも珍しくありません。
そんな時に力を発揮するのが、「事業承継税制」という特別な制度です。
そもそも事業承継税制とは?わかりやすく説明します
事業承継税制とは、中小企業が後継者に株式を引き継ぐ際に発生する、
- 贈与税(生前に株を渡す場合)
- 相続税(死亡後に株が相続される場合)
この税金の納税を“猶予”する制度です。
さらに条件を満たせば、将来的にはその税金が免除(=払わなくてOK)になることもあります。
簡単に言えば、
✅ 後継者が株を受け取っても、その場で税金を払わなくてよくなる!
✅ 会社を続けていれば、最終的には税金ゼロになる可能性も!
という、まさに事業承継のハードルを大きく下げてくれる制度です。
制度の種類:「一般措置」と「特例措置」
事業承継税制には2つのタイプがあります。
| 区分 | 特徴 |
|---|---|
| 一般措置 | 昔からあった基本的な制度(納税猶予の割合が低い) |
| 特例措置 | 2018年の改正で導入。猶予割合100%、対象範囲が広く、使いやすい! |
本記事では、多くの中小企業が利用している「特例措置」に絞って解説します。
対象となる会社・後継者の条件
事業承継税制(特例措置)を使うには、以下のような要件を満たす必要があります。
▼会社の要件
- 資本金10億円未満の非上場の中小企業
- 中小企業基本法に基づく中小企業者であること
- 資産保有型会社・資産運用型会社に該当しないこと(例:不動産賃貸のみの会社などはNG)
▼先代経営者の要件
- 承継直前に「代表権」を有している
- 会社の株式の過半数(50%超)を保有している
※親族でなくてもOKです(兄弟、社員でもOK)
▼後継者(認定承継者)の要件
- 18歳以上
- 贈与・相続時に会社の「代表権」を有している
- 承継後も引き続き会社を経営していく意思がある
- 会社の役員である(相続の場合、相続後5か月以内に就任)
このように、「代表者であること」「一定の株式を保有していること」が共通の要件になっています。
どのくらい税金が猶予されるの?
特例措置を利用すると、次のような恩恵が受けられます。
| 税目 | 猶予される割合 |
|---|---|
| 贈与税 | 100%納税猶予(=全部免除対象) |
| 相続税 | 100%納税猶予(=全部免除対象) |
つまり、評価額が1億円の株を子どもに贈与しても、贈与税ゼロ!という世界が実現するのです。
ただし、これは会社を継続して経営していくことが前提条件です。
制度を使うための手続きとスケジュール
この制度を使うには、次のような流れで手続きが必要です。
ステップ①:特例承継計画の提出(2026年3月31日まで)
最初のステップは「特例承継計画」を都道府県に提出すること。
- 誰に引き継ぐのか(後継者の名前)
- どのように承継するのか(贈与 or 相続)
- いつ頃を予定しているか
などを記載します。これは制度利用の“事前予約”のようなものと考えてください。
※提出しないと制度が使えません!
ステップ②:実際に贈与 or 相続(〜2027年12月31日まで)
提出後、計画に沿って株式の承継を行います。
- 生前贈与の場合:贈与契約書を作成し、贈与税の申告時に「納税猶予」の適用申請を行う
- 相続の場合:相続開始後10か月以内の申告で「納税猶予」の適用申請を行う
ステップ③:都道府県知事の認定
承継後、都道府県からの「認定」を受ける必要があります。
これによって、正式に納税猶予がスタートします。
ステップ④:毎年の継続届出書の提出(5年間)
株式をもらった後も、後継者がちゃんと会社を経営しているか?を確認するため、
- 会社が存続しているか
- 後継者が代表を務めているか
といった報告書類を毎年税務署と都道府県に提出します。
ステップ⑤:6年目以降は3年ごとに報告
5年間の毎年報告が終わると、6年目以降は3年に1度の報告でOKになります。
雇用維持要件とは?実務的には“ほぼ撤廃”されています
事業承継税制を使うにあたって、以前までは
「会社の従業員を5年間平均で8割維持しないと、猶予が取り消される」
という厳しいルールがありました。
しかし、これは大きく緩和されています。
✅ 今は「正当な理由」があれば維持できなくてもOK!
たとえば以下のような理由であれば、雇用が減っても猶予は継続できます:
- 業績悪化による自然減
- コロナなど外的要因による縮小
- 業態転換による合理的なリストラ など
実務上、税務署に「理由書」を添えればOKになることがほとんどです。
つまり「雇用8割維持できなかったら全部アウト」という時代は終わりました。
猶予された税金は、どうすれば“免除”になる?
事業承継税制は、「いったん税金の支払いを止める(猶予)」だけでなく、
✅ 一定の条件を満たせば、その税金を払わなくてよくなる(免除)
という制度です。
免除になるタイミングは?
たとえばこんなときに「免除」されます:
- 後継者が死亡した
- 会社を清算(廃業)した
- 10年後に第三者へ売却する(M&A)など
制度の取り消しリスクには要注意!
逆に、次のような場合は「猶予が取り消されて」、それまでの税金+利息を一括で支払う羽目になります。
❌ 取り消しになる例:
- 後継者が代表を辞めてしまった(特に5年以内)
- 株式を第三者に売却してしまった
- 継続届出書の提出を忘れた(実はこれが多い!)
つまり、猶予は「条件付き」ということです。
条件を守っていれば払わなくていいけれど、守らなければすぐにアウト。
「届け出忘れ」が一番もったいないので、顧問税理士や専門家と連携しておきましょう。
よくある誤解とQ&A
Q1. 親族以外でも使えるの?
→ はい、使えます!
社員、役員、MBOなど、親族以外の承継も対象です。
「家族が継がないから無理…」という方にも朗報です。
Q2. 株式全部じゃないとダメ?
→ いいえ、一部でもOKです!
ただし、総議決権の50%超を後継者が持つことが必要です(贈与時に)。
Q3. いったん使ったらやめられない?
→ 中止も可能です。
猶予をやめる=通常の税金を払えば、いつでもやめられます。
「一時的に納税を待ってもらう制度」と理解するといいでしょう。
制度利用の流れまとめ(再掲)
| ステップ | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| ① 特例承継計画の提出 | 都道府県に提出 | 2026年3月31日まで |
| ② 実際の贈与・相続 | 株を渡す | 2027年12月31日まで |
| ③ 納税猶予申請 | 税務署で手続き | 贈与・相続の申告時 |
| ④ 継続届出 | 年次で提出 | 承継から5年間は毎年 |
| ⑤ 免除 or 継続 | 経営継続 or 売却等 | ケースに応じて判断 |
実務上のポイントとアドバイス
- 顧問税理士に必ず相談を!
→ 事業承継税制は税務処理が複雑です。申請書類やスケジュール管理が命です。 - 「計画提出」は先に済ませる
→ 株を渡すのは後でもいいので、2026年3月末の計画提出だけは先にやっておきましょう。 - 後継者とよく話しておくこと
→ 後継者が「社長を続けられるか」「代表になれるか」は大前提です。
まとめ|後継者が困らない承継のために
事業承継税制は、中小企業の未来にとって非常に強力な制度です。
✅ 株を渡すときの税金を実質ゼロにできる
✅ 承継の負担が軽くなる
✅ 親族外でも柔軟に活用できる
一方で、制度の使い方を間違えれば、逆に大きな負担を背負うリスクもあります。
だからこそ、早めの準備と専門家との連携が大切です。
経営者として「会社を誰にどう残すか」は、最も重要な意思決定のひとつ。
事業承継税制は、その意思を現実にする強力な味方です。
気になった方は、ぜひ税理士や認定支援機関に一度相談してみてください。





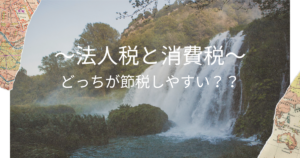

コメント