こんにちは!公認会計士・税理士の小嶋です。
当記事では「社会保険料の負担」について記載したいと思います!
現行法では、株式会社や合同会社など、すべての法人は社会保険への加入が義務付けられています。
これは、社員を雇っていようがいまいが関係ありません。すべての法人です。
それでは、社会保険料が課せられる対象はなんでしょう?まずはそこから、
「給与」と「賞与」に社会保険料が課せられる。
社会保険料が課せられる対象は、「給与」と「賞与」です。
そしてそれぞれについて、課せられる金額というのが若干異なってはきますが、
ここで一度、ところで、あなたは社会保険料とは?と聞かれて答えられますか??
実は、社会保険料という名前そのものの保険はありません。
いくつかの健康保険等、公的保険を総称して、社会保険と銘打っています。
社会全体で保険料を集めて、国民の生活を守ろうといった制度ですね。
そして、一般的な解釈として、社会保険料には「広義」のものと「狭義」のものに分けられます。
・健康保険料
・厚生年金保険料
・介護保険料
上記3つに加え、
・(労災保険料(労働者災害補償))
・(雇用保険料)
給与、賞与それぞれについて、上記の社会保険料が課せられますが、
その料率などがことなります。
以下確認していきます。
それぞれの社会保険の保険料率を、令和4(2022)年現在の状況で見てみましょう。
厚生年金保険の社会保険料率
厚生年金保険の社会保険料率は18.3%で固定されています。
過去には毎年変更が行われていましたが、平成29(2017)年以降はそのまま維持されており、現状、保険料率の上昇は予定されていません。
健康保険の社会保険料率
健康保険の保険料率は、協会けんぽのケースでは都道府県毎に、また健康保険組合のケースでは組合毎に異なります。都道府県毎の保険料率はだいたい10%前後です。
例えば令和3(2021)年度の健康保険料率は、東京都の場合9.84%、大阪府の場合10.29%です。
介護保険の社会保険料率
介護保険の保険料率は現在1.80%となっています。
これまでは全国統一の1.79%でしたが、令和3(2021)年に改定されました。今後も介護保険の保険料率は改定される可能性があります。
雇用保険の社会保険料率
一般の企業における雇用保険の社会保険料率は現在0.9%で、会社が0.6%、個人が0.3%を負担します。
しかし、農林水産業や清酒製造業では1.1%(会社が0.7%負担)、建設業では1.2%(会社が0.8%負担)となります。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で雇用保険の積立金が減っているため、保険料率が引き上げられることが決定しています。引き上げ後の雇用保険料率は1.35%で、会社が0.85%、個人が0.5%を負担します。
労災保険の社会保険料率
労災保険の保険料率は業種によって異なります。
例えば、卸売りや小売り、飲食業や宿泊業などでは0.3%、食品製造業では0.6%です。
また、林業では6%、金属工業では8.8%、水力発電施設では6.2%など、比較的高い料率が設定されています。労災保険の保険料率は定期的に改定され、今後も変更があるかもしれません。
社会保険料は誰が負担するか?会社負担の話。
上記にも一部記載しましたが、社会保険料は、「会社」と「給与・賞与を受け取る個人」とのそれぞれ負担割合があります。
この分担の割合は、保険の種類によります。
企業は従業員の給与を算出し、そこから従業員が負担する社会保険料を差し引きます。
その上で、企業の負担分を加えて、社会保険料として納付します。
現行の制度では、厚生年金保険料や健康保険料については、企業と従業員がそれぞれ半分ずつ負担します。
また、40歳以上65歳未満の従業員に対しては介護保険料の一部も負担が必要です。
雇用保険料は企業が多くを、労災保険料については企業が全額を負担します。
これら全ての社会保険料を合わせると、企業の負担割合は概算15~16%程度になります。
加入しないとどうなるか?罰則はあるのか??
- 「起業したばかりですが、社会保険へ加入しなくてはならないのでしょうか?」
-
「基本Yesですが、ケースによってはNo」です。
健康保険と厚生年金保険は、
事業所を単位として、加入が義務づけられる「強制適用事業所」と、
任意加入の「任意適用事業所」の2種類に分類します。
任意適用事業所に該当すると、加入義務が無いのです。
それぞれの違いについて説明していきます。
強制適用事業所
・法人事業所(株式会社などの会社組織)
・個人事業主で従業員数が5名以上の事業所
ただし任意適用事業所に指定される業種以外の事業所が対象
ということで、スタートアップのような比較的従業員数が少ない組織であっても、株式会社等の法人事業所であれば強制適用が義務付けられています。
任意適用事業所
従業員が5人未満の個人事業所

※任意適用事業所の認可を受けるには、その事業所の従業員の半数以上の同意を得なければなりません。同意があれば、加入を希望しない従業員も含めて全員に適用することになります!
・個人事業主が運営する従業員5名以上の事業所(かつ、以下の業種に該当する事業所)
強制適用事業所で、加入義務を怠ったらどうなるか??
強制適用事業所に該当するにも関わらず、社会保険へ加入しない場合には当然罰則があります。
各社会保険の罰則は以下のようになっています:
雇用保険 :違反者に対し、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
健康保険 :違反者に対し、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
厚生年金保険:違反者に対し、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
労災保険 :違反者に対し、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
もし違反が発覚した場合、最大で2年間遡って社会保険への加入が求められ、その期間にわたる保険料を支払う必要があります。
社会保険に加入する方法
社会保険への加入手続きは簡単です。
健康保険および厚生年金保険については、日本年金機構のサイトを確認の上、準備・作成し、管轄の年金事務所または日本年金機構に郵送するか、窓口に持参してください。
また雇用保険、労災保険については、管轄のハローワーク、労働基準監督署にて手続きを行うことができます。

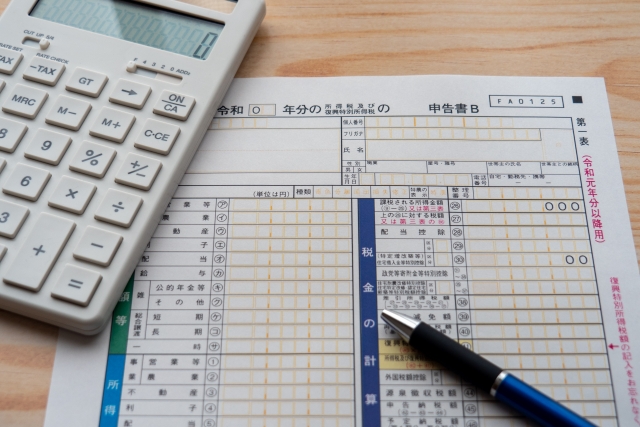


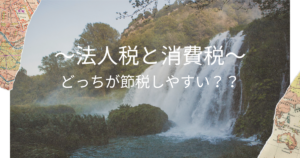


コメント